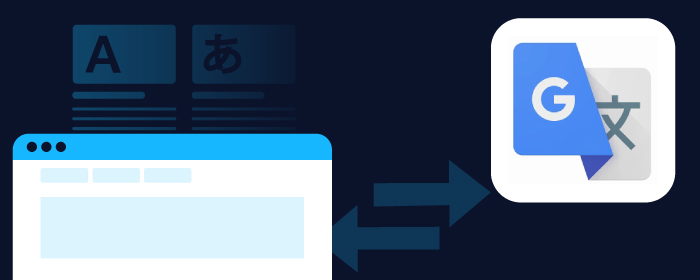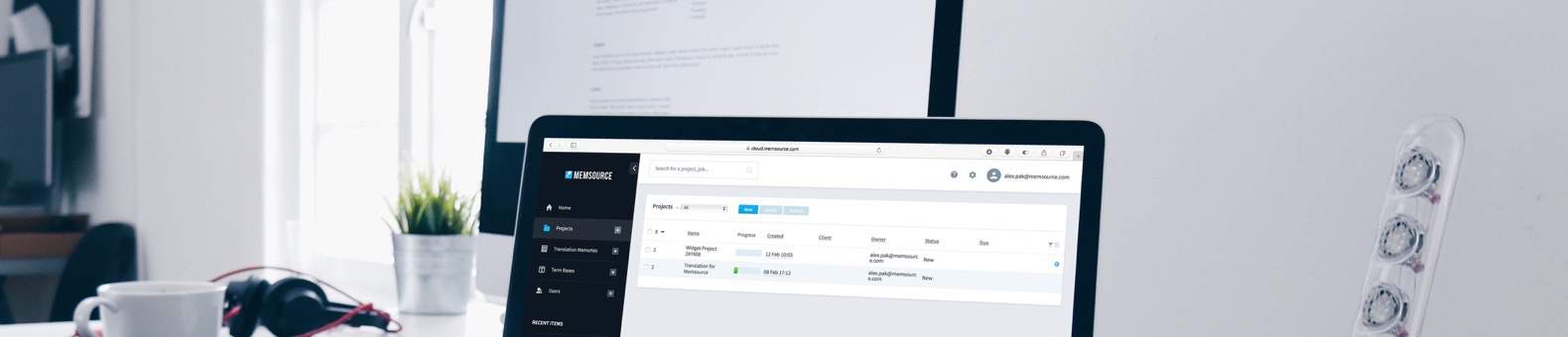
日本窓口よりメムソースお役立ち情報ブログ
目次
Memsourceは初めてですか?

ビジネスを海外展開する際の出発点となる多言語サイト。そのメリットや基本的なアプローチ、作成にあたっての注意点などをまとめました。
海外市場への進出を目指す企業にとって、自社サイトの多言語化は新しい世界への扉を開く第一歩です。しかし、ただ言語を変換するだけでは、本当に効果的なサイトになるとは言えません。そこで本記事では、実際のビジネスで多言語サイトを作成する際に、押さえておくべきポイントをお伝えします。
多言語サイトとは?
多言語サイトとはその名の通り、複数の言語に対応したウェブサイトのことです。たとえば、日本国内でビジネスを行なっている企業が海外進出を検討する際に、自社のサイトを多言語化することで、ターゲットとする国や地域に向けて情報を発信できます。成功するグローバルマーケティングに向けての第一歩となる施策です。
多言語サイトとグローバルサイトの違いは?
業界で使われる用語として「多言語サイト」の他に「グローバルサイト」という言葉もあります。これらはどう違うのでしょうか?
多言語サイト:
上記のように、2つ以上の言語に対応したサイト。ビジネスを展開したい対象地域に向けて、現地の言語で情報を発信することを目的とします。
グローバルサイト:
特定の国や地域によらず、全世界をひとつの市場とみなして、共通した企業情報やビジョン、製品情報などを発信するサイト。必ずしも複数言語でなくてもよく、たとえば世界の共通語として、英語のみでグローバルサイトを構成することもあります。また、トップにグローバルページを設けて、そこから各地域のサイトへと誘導するような構造も多く見られます。
なぜ多言語サイトが必要なのか?
国内で事業を行っている場合、自社のサイトで、商品やサービス、会社情報などを紹介しているケースが多いでしょう。ブログなど定期的に更新するコンテンツがある場合や、SNSのアカウントとリンクさせている場合もあるかと思います。国内向けのサイトとしては、これで十分に役割を果たします。
ただ、当然ながら、情報が届くのは日本語を読める人に限られます。サイト自体はインターネット上にあり、仕組みとしてはつながっているのに、他言語の話者からは全く見えない存在になっているわけです。世界人口に占める日本人の割合は約1.6%。インターネットが持つ大きなポテンシャルが手付かずのまま残されているとも言えます。
もちろん、多言語化したら、すぐに商品が飛ぶように売れるようになるとは限りません。しかし、その扉を開けなければ何も始まりません。可能性に満ちた世界への扉を開く鍵、それが多言語化です。
多言語サイトには、どんなメリットがある?
最大のメリットは、サイトへの来訪者数が増えることです。たとえば日本国内で事業を行っている会社は、サイトを多言語化することで、海外から引き合いがあったり、商品やサービスが売れるようになったりするかもしれません。
ただちにビジネスにつながらなくても、企業や商品、ブランドの認知度が上がることで、今後のビジネスを展開しやすくなる利点もあるでしょう。情報を発信することで海外とのやり取りが生まれ、そこから潜在的なニーズを掴める可能性もあります。つまり、グローバルな新規市場開拓に役立つと言えます。
また、海外事業に本気で取り組んでいる姿勢を表すことで、国内からの見方も変わり、新たな機会やコラボレーションにつながることも考えられます。これらすべての可能性を拓く突破口となるのが多言語化なのです。
多言語サイトのデメリットや課題とは?
多言語化にはデメリットや課題はないのでしょうか? デメリットとまでは言いませんが、以下の点は考慮に入れておく必要があるでしょう。
- ローカライズ作業のコスト
多言語化を行うには、当然ながらコストがかかります。いくら社内に言語に堪能な社員がいても、すべての作業を担うのは現実的ではありません。デザイン面でも多言語化に慣れたデザイナーやエンジニアに依頼することで、より効果的かつスムーズにサイトを構築できます。このような社内外のリソースを活用するための投資が必要になってきます。業務を効率化するツールの利用も役立つでしょう。
- 問い合わせへの対応体制
海外からのアクセスが増えると、引き合いや問い合わせが増えることが予想されます。そのときに対応する体制が十分でなければ、せっかくのチャンスを逃してしまうことになりかねません。カスタマーサポートなど、アクセスを集めた後の対応も視野に入れて、計画を練っておくことが重要です。
実際の多言語サイトの例
では、実際に企業はどのような多言語化を行なっているのでしょうか?
国内企業では、たとえば、サイボウズ株式会社は、自社サイトを日英中3言語で展開。製品の多言語化も進めるとともに、主に中国、ベトナム、米国に拠点を置いて、アジアや欧米地域での販売に取り組んでいます。頻繁に更新のあるヘルプサイトやリリースノートなどのローカライズは、最新のツールを使って効率的に作業を行なっています。
海外企業では、たとえば、Appleのサイトは世界中の言語への対応はもちろん、どの言語でも美しく見えるようにデザインされています。アプリの制作者も、アプリを多言語化できる仕組みになっています。
多言語サイト作成の具体的な進め方とは?
では、具体的にサイトの多言語化に取り掛かろうと思ったら、何から始めればよいのでしょうか? 以下のようなポイントが挙げられます。
言語を選ぶ
まず、対象とする言語を選ぶ必要があります。日本企業が海外展開を考える場合には、まず英語が思い浮かぶでしょう。英語のウェブサイト数は世界の全ウェブサイトの6割以上を占め、圧倒的な1位であることを考えても、妥当な選択だと言えます。
ただ、実際の世界におけるウェブ上の英語話者ユーザーは25%にとどまるという調査結果もあり、その他の言語への潜在的なニーズが高いことも推測されます。とくに中国語話者は英語に迫る20%近くの割合を占めています。
そのため、とくに市場開拓のターゲットとしている地域や、自社サイトのアクセス解析などから関心が高いとわかった地域など、英語以外の言語を含めた多言語化も検討する価値があります。
対象地域のオーディエンスを知る
事前にその言語話者の市場について、できる限り学んでおくことも大切です。現地の購買者の好みや人口構成、金銭感覚、その市場で同じような事業を行なっているローカル/グローバルの競合他社の動向、その国の規則などについて調査し、どのようなアプローチで進出すればよいか、戦略を検討します。
対象のコンテンツを絞る
すべてのコンテンツを多言語化しようとすれば、時間も手間もコストもかかってしまい、その遅れがチャンスを失うことにつながる恐れもあります。そのため、調査結果や事業戦略をもとに、これぞというコンテンツやページに絞って、まずはそこから着手するのがポイントです。実際、国内外の多くの企業が、コンテンツを絞ったアプローチでサイトの多言語化を行っています。
翻訳を超えたローカライズを行う
もうひとつ重要なアプローチが、ローカライズです。ローカライズとは、単なる翻訳の枠を超えて、現地の文化に即してコンテンツ全体をアレンジしていく方策のこと。多言語化=翻訳という考えに留まらず、より広い視野でのローカライズ戦略が重要です。
海外発のサイトで、たしかに文字は日本語になっているのだけど、何か雰囲気がしっくりこない……という印象を持たれたことのある方もいるでしょう。これこそがローカライズが不足している状態。現地ですべて手作りしたレベルにまで完璧にローカライズするのは現実的ではないかもしれませんが、できるだけ文化を理解しよう、現地の人のために何かを提供しようという姿勢はコンテンツを通じて伝わり、オーディエンスの共感や親近感につながります。
以下で、さらに具体的なポイントを見ていきましょう。
多言語サイト作成時のローカライズのポイント
文章のローカライズ
文章を翻訳・ローカライズする際には、現地の文化やマーケットに精通したリンギスト(翻訳者、校正者、ライター)に依頼するのがベストです。
また、最近のビジネス分野では機械翻訳(MT)の導入も進んでいますが、どの世界でも基本的には、人は機械よりも人間に話しかけられたいと思うもの。機械翻訳を使う場合も、経験のあるリンギストが後編集(ポストエディット)やリライトを行うことで、情報の正確性を担保でき、より人間味のある文章を作成できます。背景や歴史の把握という機械翻訳が苦手とする部分を、人間主導で補っていく必要があるでしょう。
また「翻訳」で起こりがちな一文単位で意味を合わせていくアプローチを超えて、コンテンツ全体として情報やストーリー、メッセージ、キャッチコピーなどを効果的に伝えていくという「トランスクリエーション」の視点も大切です。目的に応じて、文化やデザインなどを考慮した創造的な文章作成を行っていくこともポイントになります。
デザイン、仕様のローカライズ
たとえば、日本向けには情報密度の高いサイトが好まれ、欧米向けには、より余白の多いシンプルなデザインが好まれる傾向があるといったように、対象となるオーディエンスに適したデザインにすることも大切です。ブランドとしての統一感とのバランスを維持しながら、ローカライズを行うことがポイントになります。
また、翻訳を行うと、言語によって文章の長さが変わり、オリジナルの言語では美しく配置されていたデザインが崩れてしまうことがあります。この場合、デザインの微調整を行ったり、あらかじめ多少の文章の長さの変化に影響を受けない設計にしておくことで、現地の人が見て違和感のないサイトやページに近づけるでしょう。また、世界中の文字をひとつのコード体系で扱えるUnicodeを使うことで、どの言語でも文字化けを防ぐことができます。
多言語サイトのSEO対策とは?
あわせて欠かせないのが、SEO対策です。SEOというと難しく聞こえるかもしれませんが、簡単に言うと、サーチエンジンから自社のサイトがどう見えるかを調整していく施策のこと。検索エンジンに正しく見つけてもらい、そのコンテンツを本当に求めている人に確実に届けるための方法です。
具体的には、画像内のaltテキストや、metaタグ内のタイトル・ディスクリプションのローカライズ、言語ごとのURLの設定やコードの調整、重複コンテンツではなくバリエーションであることを示すタグの設定などが挙げられます。
たとえばGoogleの検索エンジンは、基本的にはコンテンツの内容から言語を自動的に判断していますが、タグによってページの存在と言語をGoogleに伝えることで、特定言語でのページランクの上昇につながります。
また、機械翻訳そのままのページだとサーチエンジンの評価が下がる恐れがあるため、文章自体のローカライズもページの評価に関係してきます。検索結果の上位に表示されるためには、その言語の話者が実際に使っているキーワードを調べ、タイトルや見出し、本文に含めることも重要です。
さらに、世界的に利用されているGoogle以外にも、中国語ではBaidu、韓国語ではNAVER、ロシア語ではYandexなど、地域によって人気のある検索エンジンがあることも、押さえておく必要があるでしょう。
多言語サイトを作成する際の注意点
その他にも多言語サイトを作成する際には、いくつか注意すべき点があります。
現地の文化や習慣
その言語を話す人が見てわかりやすいデザインや表記、言葉遣いを採用しましょう。その地域の文化や宗教、多様性などへの配慮も重要です。また、必ずしも言語イコール国ではないため、国旗のアイコンを使う際には注意が必要になることがあります。
現地の通貨、支払い方法
国や地域によって通貨が違うのはもちろんのこと、好まれる支払い方法も異なります。現地の商習慣に対応していなければ、せっかくオーディエンスが興味を持ってくれても、直接の購買にはつながりません。
たとえば、世界のオンライン購買の支払い方法としては、Visa/Mastercard(世界のオンライン売上の68%)、PayPal(同19%)、American Express(同7%)がよく使われていますが、オランダでは43%の購入者がiDEALでの支払いを、中国では42%の購入者がAlipayでの支払いを好むといった、地域による特性も見られます。
また、コンテンツの文章内で金額に言及する際には、現地通貨に換算した額を併記することで、よりわかりやすくなるでしょう。
数値や単位の形式
通貨、日付、長さや重量の単位、数値の省略単位(K=1000、M=100万、B=10億)、住所、電話番号なども、現地の表記に合わせることで混乱を防げます。
たとえば、日付は、同じ英語圏でも「月/日/年」の順に並べる地域(北米)と、「日/月/年」の順の地域(イギリス、オーストラリアなど)があり、数字を並べるだけでは日付を間違う恐れがあります。とくに「月」は日本のような数字よりも、January(Jan)、February(Feb)などと英単語で表記する方が誤解がないでしょう。
法律や規制
各国・地域で定められている規制や法律を理解しておくことも大切です。たとえば、EU圏では「一般データ保護規則(GDPR)」により、域内で取得した氏名やメールアドレス、クレジットカード番号などの個人情報を域外に持ち出すことが原則禁止されています。米国ではカリフォルニア州で消費者プライバシー法(CCPA)が施行され、同様にプライバシーに関する権利を保護しています。
多言語サイトで成功するには?
ここまで説明してきた内容からもわかるように、多言語化から十分な成果を引き出すには、配慮の行き届いた質の高いサイトを作成する必要があります。ただ、それを実際の業務で行うとなると、作業が煩雑になることが予想されます。
そのため、現在のビジネスの現場では、翻訳・ローカライズ業務をできるだけ効率的に行うためのツールが使われるようになっています。そのひとつが、翻訳業務に特化した「翻訳管理システム(TMS)」です。
翻訳管理システムでは、複数プロジェクトの管理が容易になるほか、外部のリンギストとの共同作業も効率的に行えます。翻訳メモリや用語集といった翻訳支援ツール(CAT)も利用でき、機械翻訳の導入もスムーズ。クラウド型の翻訳管理システムなら、会社を超えたコラボレーションやリモートワークにも便利です。
一方、ウェブサイトや企業ブログなど、デジタルコンテンツの作成・配信・管理に広く使われているシステムが「コンテンツ管理システム(CMS)」です。このCMSと翻訳管理システムを連携させることで、多言語コンテンツの作成・管理をより効率的に行えるようになります。CMSと翻訳管理システムの組み合わせが、現在の動きの速いビジネスに対応しやすい多言語化ソリューションだと言えるでしょう。
終わりに
今回は多言語サイトについて、そのメリットや課題、具体的な作成に向けての注意点などを見てきました。グローバル化という言葉が広まってから随分時間がたったようにも感じますが、実際にはまだまだ多くの情報が言語の壁の内側にとどまっています。その壁に少しでも穴を開けることで、新しい世界の可能性が見えてくるのではないでしょうか。企業や組織の多言語化への取り組みが、最終的に世界の風通しの良さにつながることを期待しています。