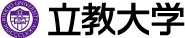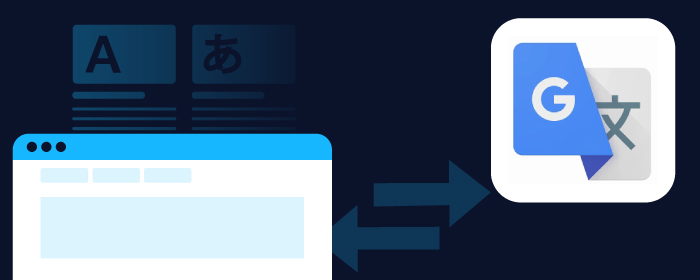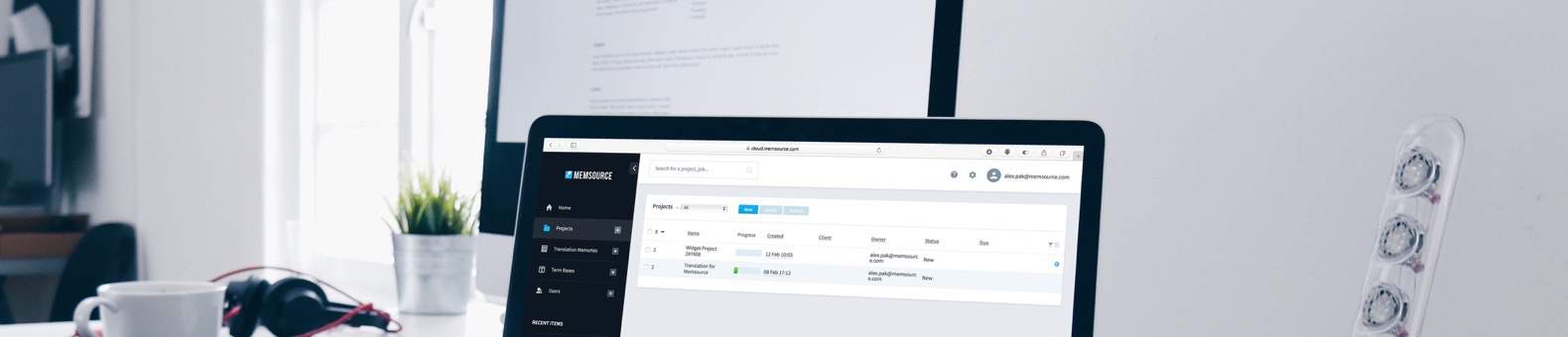
日本窓口よりメムソースお役立ち情報ブログ
Memsourceは初めてですか?
 立教大学Tony Hartley教授(翻訳テクノロジー研究)は、同大学大学院異文化コミュニケーション研究科に今年度開講された新科目「翻訳通訳テクノロジー論」の教育理念を、次のように語ります
立教大学Tony Hartley教授(翻訳テクノロジー研究)は、同大学大学院異文化コミュニケーション研究科に今年度開講された新科目「翻訳通訳テクノロジー論」の教育理念を、次のように語ります
「『訓練』とは特定のタスクやツール活用における熟練度を伸ばすことです。それに対し、様々なアプローチをそれぞれ評価、比較して最善の方法を選択する能力を育むのが『教育』です。学生は『教育』によって、何らかのタスクを行う際やタスクに相応しいツールを選ぶ際に、適切な判断を下せるようになります」
「Memsourceは私たちの教育理念を実現するのに理想的なツールです」
Hartley教授はMemsourceのインターフェースがとてもわかりやすく、学生が初めて触れる翻訳メモリおよびプロジェクトマネジメントのツールとして、とても優れている点を指摘します。
「ウェブアプリケーションだということも私たち教育機関にとっては有難い点です。 ソフトウェアのインストールが必要ないので管理上の手間が大きく省けます。」
「翻訳通訳テクノロジー論」の大きな特徴は、学生に同類のアプリケーションをそれぞれ評価、比較する技術を身につけさせるということです。
しかし、それと等しく重要なのが、役割が異なるアプリケーション同士の接続(インターオペラビリティ)の問題です。
「これはMemsourceの得意とするところでした」とHartley教授は述べます。
「学生がSketchEngineをもとに対訳コーパスから用語集を利用したり、パートナー提携をしているSystranやNICTの機械翻訳エンジンを参照したりできるのはとても便利です」
将来的に他の翻訳支援ツールを使う機会ができた時にも、Memsourceならデータのインポートやエクスポートが簡単にできるということも利点の一つに挙げられました。
「また、翻訳プロジェクトの進め方を効率的に学べるツールでもあります」 と、Memsourceのプロジェクト管理ツールとしての側面も高く評価して頂きました。
立教大学大学院異文化コミュニケーション研究科は、武田珂代子教授の指揮下、今年度、翻訳専門職・会議通訳者養成プログラム(修士課程)を新設しました。
欧州翻訳修士(European Master’s in Translation)プログラムで培われたノウハウをもとに、ISO17100に定義される翻訳者コンピタンス要件を満たす翻訳教育に取り組んでいます。