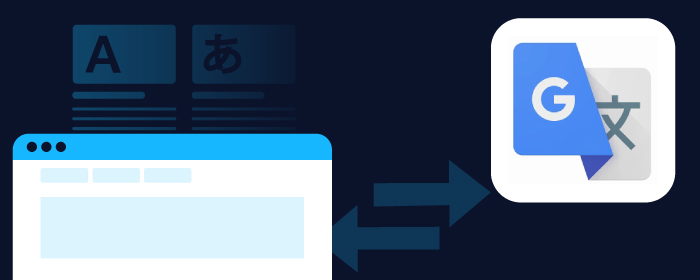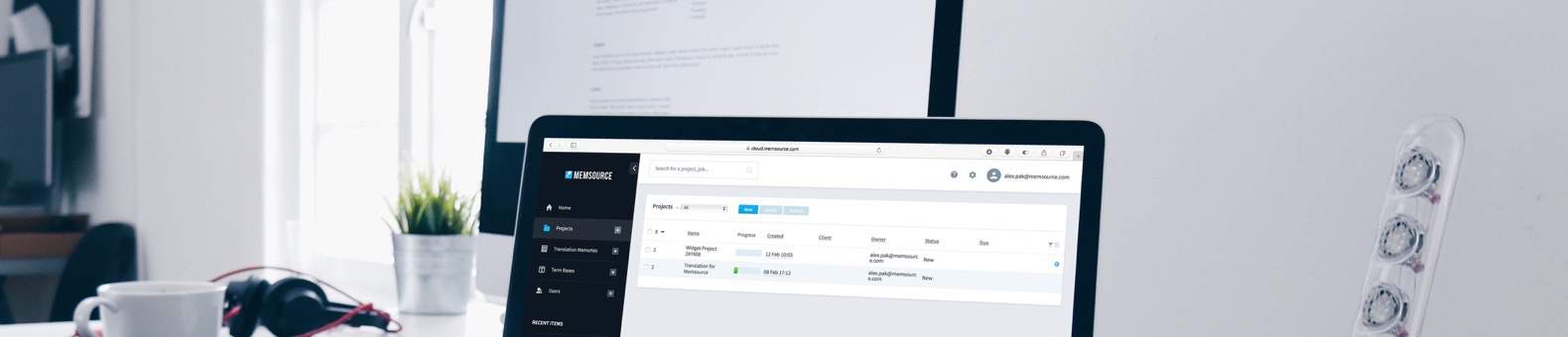
日本窓口よりメムソースお役立ち情報ブログ
目次
Memsourceは初めてですか?

製品やサービスの海外展開時に必要となるのが、マニュアル(取り扱い説明書)の多言語化です。そのコツや注意点など、マニュアル翻訳ならではの重要ポイントをまとめました。
さまざまな業界でビジネスがグローバルに展開されるようになっている今、国や地域を超えて製品やサービスを提供する際に欠かせないのが、マニュアル(取り扱い説明書)の多言語化です。製品・サービス自体が適切にローカライズされていることがまず重要ですが、その上で、いかに正確でわかりやすいマニュアルを提供できるかも、現地の新しいユーザーに受け入れられるための鍵を握ります。今回はこのマニュアル翻訳について、掘り下げてみたいと思います。
マニュアル翻訳で押さえておきたいポイントとは?
製品・サービスの使用に直接関わるマニュアル翻訳でまず求められるのは、正確性です。翻訳のミスが誤った製品利用につながり、ユーザー、自社、ひいては社会に多大な影響を与えてしまう恐れがあります。ユーザーの混乱を招かないような明瞭な表現や用語の統一も重要です。
同時に、製品のあらゆる機能を網羅し、対象言語も多くなるマニュアルでは、文書のボリュームが大きくなるため、効率的な翻訳作業も求められます。とくに近年は、短期間で素早く構築し、小刻みにリリースする製品開発のアジャイル化が進んでおり、それに合わせてマニュアルの更新・改訂作業も頻繁に生じるようになっています。
このような背景を持つ現代のマニュアル翻訳でポイントになるのは、次のような要素です。
用語集
マニュアル翻訳を行う際に、まず作っておきたいのが用語集です。マニュアル内で表記がブレてしまうと、ユーザーによる理解や操作に影響を与えてしまいます。そこで、統一すべき用語について、あらかじめ訳語を定めて、用語集としてまとめておきます。これにより、実際の製品とマニュアルで表記が異なっている、といった混乱も防げます。
原文と訳文のシンプルな対訳表をスプレッドシート等で用意しておくとよいでしょう。その際に、実際の使用例や文脈など、背景情報の説明を付記しておくと、作業者間で意図を共有でき、例外処理などの判断もしやすくなります。プロジェクトを進めながら、用語集を随時追加・更新していくことで、常に最新の情報を参照できるようになります。
スタイルガイド
用語集とあわせて用意しておきたいのが、スタイルガイドです。同一の文書内でトーンや表記が揺れてしまうと、ユーザーの混乱を招くだけでなく、文書や製品に対する信頼性も揺らいでしまいます。また、文書ボリュームが大きくなるマニュアル翻訳では、複数の翻訳者、校正者、管理者による分業体制がとられることが多くなります。その場合でも、統一感のあるマニュアルを継続的に作っていくために、スタイルガイドが役立ちます。
スタイルガイドとは、その名の通り、文章のスタイルをあらかじめ定め、翻訳作業時のガイドとしてドキュメントにまとめておくものです。作業者はそれを参照することで、統一したスタイルで翻訳文を作成していけます。
具体的には、表記のルールや表現のトーンについて方針を定めます。例えば日本語なら、常体・敬体のどちらを用いるのか、ヘッドラインや箇条書きの文体、数字や記号、半角・全角、漢字・ひらがな・カタカナ・英文字の使い分けなど。英語であれば、大文字・小文字の使用、主語は何を使うか、カジュアルなのかフォーマルなのか……といったことを記載します。想定されるユーザー像の定義も、表現の判断材料として役立ちます。実際の製品との表記の統一や整合性についても定めておくと良いでしょう。
ただ、あまり細かく規定してしまうと、自由度が失われ、かえって効率や品質にマイナスの影響を与える可能性もあります。まずは頻繁に出てくるパターンから優先して記載し、プロジェクトを進めながら随時更新していくことで、洗練されたスタイルガイドになっていきます。
機械翻訳
近年、日進月歩の進化を見せている機械翻訳。とくに定型表現が比較的多く、学習用の対訳データも確保しやすい技術系のマニュアルは、機械翻訳が力を発揮しやすい分野だといえます。凝った言い回しよりもシンプルな表現が求められるマニュアルでは、機械翻訳の出力を活用できる割合も多くなり、作業のスピードアップにつながるでしょう。
ただ現状では、機械翻訳は、まだビジネスでそのまま使える品質レベルには達していません。そのため、正確性が求められるマニュアル分野では、人間によるレビューやポストエディット(後編集)の工程が不可欠です。一見、流暢だけれど意味が真逆になっていたり、固有名詞を間違えていたりといった、人手翻訳では考えにくいミスが起こるケースもあるため、十分なチェック体制を敷いておくことが重要です。
ワークフローの確立
マニュアル翻訳業務では、製品開発と連動したシビアなスケジュール管理や、急な仕様変更などへの臨機応変な対応が求められます。タイトな日程でも品質を落とさないためには、しっかりとしたワークフローを構築しておくことが土台になります 。ただ翻訳者に依頼するだけではなく、原稿準備、翻訳者の割り当て、機械翻訳の適用、ポストエディット、校正・レビュー、編集、最終チェックといった工程を確実に踏めるよう、自社の業務に合わせたワークフローを固め、効率的に管理できる体制を作りましょう。
マニュアル翻訳を行う前に確認することとは?
マニュアル翻訳業務を担当することになったら、まず何を確認すればよいのでしょうか? 翻訳作業に着手する前に、以下のような点をチェックしておきましょう。
過去の翻訳資料
まず、これまでに翻訳された類似のマニュアルを集めましょう。表記やトーンの統一用に翻訳者に提供する参考資料になるほか、用語集やスタイルガイドを作成する際の情報源にもなります。用語が過去のマニュアルと統一されていることで、継続して利用しているユーザーの混乱を招くこともなくなります。データベース化すれば、後述する翻訳メモリとしても活用でき、作業をさらに効率化できます。
対象となる国・地域やユーザーのリサーチ
翻訳作業を開始する前に、対象となる国・地域やターゲットユーザーについて理解しておくことも大切です。
対象ユーザー
マニュアルは、大きくエンドユーザー向けのものと、技術者・専門家向けのものに分けられます。例えば、技術者向けのマニュアルなら専門用語をそのまま使い、初心者を含むエンドユーザー向けなら補足を加えたり噛み砕いて伝えたりするなど、対象読者の知識度合いを把握することで、より適切な用語や表現を選択できます。
対象国・地域
国や地域によっては、マニュアルの記載内容について規定がある場合があります。例えば、中国では「GB規格」によって、取扱説明書も製品の一部とみなされ、記載事項や記載方法が規定されています。このように対象となる国・地域のルールについて、あらかじめリサーチしておくことが重要です。規定に対応した表現をスタイルガイドに記載して、作業者間で共有すると良いでしょう。
社内でマニュアル翻訳を行うには?
マニュアル翻訳の業務は、自社で翻訳を行うか、翻訳会社に依頼するかの2通りの方法があります。ここでは、まず社内で行う場合を考えます。
上述したように、マニュアル翻訳では、用語の統一など正確性の確保、大量の文書の効率的な処理、確実なワークフローの管理が求められます。これらの実現に役立つのが、翻訳管理システム(TMS:Translation Management System)の導入です。
翻訳管理システムとは、翻訳業務に特化した業務管理システムのことです。多くの場合、プロジェクト管理機能に加えて、翻訳エディタ、翻訳メモリ、用語ベースといった翻訳支援(CAT)ツールが付属しています。
翻訳管理システムでは以下のような機能を活用できます。
用語ベース
用語ベース(TB:Term Base)とは、特定の用語について、あらかじめ訳語を指定しておくデータベースのことです。登録された用語が登場すると、翻訳エディタ上でその箇所と適切な訳語を教えてくれます。翻訳中に随時、用語を登録することも可能です。品質保証機能を利用すると、用語が正しく反映されているかどうかを自動でチェックしてくれます。
この用語ベース機能により、1つの文書内での用語の統一はもちろん、複数の文書や作業者間を横断して、表記を統一しやすくなります。補足情報も記載できるため、背景や使用例などの情報共有にも便利です。スプレッドシートで用意した用語集をシステムに読み込ませることで、用語ベースとして活用できるようになります。
翻訳メモリ
翻訳メモリ(TM:Translation Memory)とは、翻訳した文章を、原文と訳文のペアで保存していくデータベースのことです。これにより以降の翻訳時に、原文と完全または部分的に一致する文章をメモリから自動検索して、訳文を再利用できるようになります。以前と同一または似たような文章を、何度も翻訳し直す必要がなくなり、作業時間を短縮できます。
過去訳との表現の統一にも役立つほか、メモリはプロジェクト間で簡単に共有できるため、複数の文書、作業者の間で統一を図る際にも力を発揮します。手動でデータベース内を検索することもできるため、適切な表現方法を探したいときにも便利です。
とくにマニュアル翻訳では、文書の一部だけが改訂されるアップデート作業が頻繁に生じます。その際にも翻訳メモリにより変更点が一目でわかり、変更のない部分は過去訳を再利用できるため、作業効率が大幅にアップし、人間によるケアレスミスも防げます。
機械翻訳
機械翻訳エンジンとの連携機能がある翻訳管理システムでは、システム内で機械翻訳の出力を利用できます。前述のように、マニュアル翻訳は機械翻訳が力を発揮しやすいジャンルですが、エンジンによって得意・不得意とする分野があるため、最適なエンジンの選択が重要です。翻訳管理システムによっては、コンテンツに応じて最適なエンジンを自動で選択してくれる機能もあります。ただ、どのエンジンを利用する場合も、ビジネスレベルで用いるには正確性の面で課題があるため、人間によるポストエディット(後編集)の工程を必ず加えましょう。
ワークフローの管理・自動化
マニュアル翻訳は比較的工程が規則的であるため、ワークフローの自動化を図りやすい分野です。多くの翻訳管理システムに備わっているワークフローの自動化機能を使うと、1つのステップが完了すると、次の作業者に通知が送信され、自動的にプロジェクトが進んでいきます。
自動化により、管理者は単純作業を省いて、複数のプロジェクトを同時進行しやすくなり、翻訳者・校正者もより重要な作業に集中できるようになります。文書内のセグメントごとにコメントのやり取りができるため、変更点をPDFにマークして伝えるなどの必要もなく、作業者間のコミュニケーションもスムーズになります。
翻訳会社にマニュアル翻訳を委託するには?
社内で業務を行うリソースが足りないときは、翻訳会社に委託することになるでしょう。その場合も、翻訳管理システムを使うことで業務管理がしやすくなります。
複数ベンダーによる作業の管理
翻訳会社ごとに得意とする言語や分野があり、対応できるキャパシティも変動することが考えられるため、複数の会社(ベンダー)に翻訳業務を委託するケースが出てくるでしょう。その場合も、翻訳管理システムを導入することで、1つのシステムで複数のベンダーへの作業委託を一元管理できます。
原文ファイルや翻訳メモリ、用語ベース、参考資料なども、システム上で数クリックで共有できるため、複数ベンダーを横断して一貫した品質を保てます。翻訳メモリを共用することで、翻訳資産としても効率的にデータを蓄積していけます。
各作業の進捗状況もリアルタイムで確認できます。ベンダーを変更しても同様の手順で業務を進められ、ワークフローの自動化により、少ない人員でも多くのプロジェクトを管理しやすくなります。
安全なデータのやりとり
外部のベンダーにファイル等を共有する場合、従来のメール添付でのやり取りだと、手間がかかるだけでなく、宛先間違いやウイルスなど、セキュリティ面での不安が残ります。連絡忘れや見逃しといったヒューマンエラーで業務が滞るリスクもあります。
クラウド型の翻訳管理システムを利用すると、ファイルの共有やメッセージのやり取りをクラウドシステム上で行えるため、情報漏洩やメールの誤送信といったリスクを排除でき、共同作業が安全・スムーズになります。
ワークフローのカスタマイズ
翻訳管理システムには、自社の業務に合わせてワークフローをカスタマイズできる機能があります。これにより、データの受け渡しや読み込み・書き出し、連絡といった反復作業を自動化でき、さらに生産性を高められます。具体的には以下のようなワークフローの自動化により、時間とコストを節約できます 。
- 新しいコンテンツを検知して、プロジェクトを自動作成
- AIによる過去の実績に基づいた最適なベンダーや翻訳者、校正者の自動選定
- 翻訳メモリや機械翻訳の活用、翻訳不要箇所の自動検知による事前一括翻訳
- 自動での文書解析と価格設定
- ベンダーや翻訳者、校正者への自動メール通知
- 複数のベンダーに同時打診して、早いもの順でジョブを割り当て
また、外部ツールとの連携機能を活用すると、外部ストレージやコンテンツマネジメントシステム(CMS)内のファイルの更新を検知して、自動的に変更部分をシステムに読み込み、翻訳プロジェクトを立ち上げ、翻訳完了後に指定のファイルを更新する、といった一連の作業を完全自動化できます。
効率的かつ高品質なマニュアル翻訳を行うには?
今回はマニュアル翻訳について、業務を行う際のコツや注意点、ベストプラクティスを見てきました。動きの速い今日のビジネス世界では、製品開発の高速化、高頻度化が進み、マニュアル翻訳でも効率性の向上が求められています。同時に、多くのユーザーの拠り所となる情報としての正確性や明瞭さといった品質も極めて重要です。
この2つの課題を同時にクリアするためには、今回解説した機械翻訳、翻訳メモリ、用語ベースといった翻訳テクノロジーを最大限に活用し、ワークフローを可能な限りシームレスにしていく必要があります。それらを一度に実現できるツールが、翻訳管理システムです。
とくにクラウド型の翻訳管理システムは、場所やデバイスを選ばず、最新のデータにアクセスできるため、新しい時代のリモートワーク・ハイブリッドワークにも対応しやすく、部署や会社、タイムゾーンを超えたコラボレーションにも便利です。流動性が増していくビジネスに対応しやすいツールだといえるでしょう。
グローバル化が進む中、現地のユーザーにとって、より有益なマニュアルをよりタイムリーに提供することで、優れた製品やサービスが世界中の多くの人々に利用され、世の中の発展に貢献していくことを願っています。